学年のスペースには、ところ狭しと「夏の子供たちの作品」が並んでいます。1年生は、早速、お互いの作品を見合っていました。特に初めてである1年生の保護者の皆さんは、たいへん悩まれたことでしょう。




2学期始業式(9月2日)
第2学期の始業式が行われました。校長からは、昨年度の「心のコップの話」を確認し、「ワンピースのありがとう」「パラリンピックから」の2つについて話しました。1学期から「わたしもみんなも育つ学校」になってきているので、2学期は「もっと面白い学校」にしてきましょうと伝えました。
「2学期にがんばりたいこと」では、6人の各学年の代表者が堂々と話してくれました。ちゃんと覚えてきて、準備して挑戦してくれました。この経験で、また成長していきます。


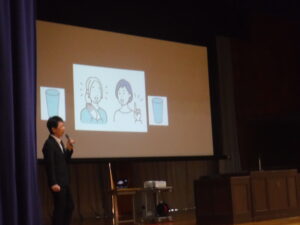









最後に、夏の派遣事業で「登米市」「広島市」を訪れた6年生の5名が、そこで感じたことを発表しました。とても貴重な経験をし、深く考えてきたことが伝わりました。5年生も今日の話を聞いて、来年派遣事業に希望してくれることでしょう。
子供たちの話を聞く姿勢にも成長を感じました。2学期もすくすくと、いろんなことに挑戦してほしいものです。






給食だより【9月】
台風10号についての対応【8月30日】
9月2日(月)は「通常どおり」に授業を行います。特別な措置は実施しません。
登校する際には、台風による破損等の被害がある場合がありますので、慌てず安全に十分留意して登校するようにしてください。
入善高校前から入善小学校前の道路が開通し、交通量が増えています。
送迎される場合は、体育館駐車場での乗り入れをお願いします。
今後、状況が急変した場合には、対応について「あんしん・安全メール」及びこのHPにて、お知らせいたします。
台風10号接近についての対応【8月30日】
台風10号の接近について、最新の気象情報を確認しながら協議しております。
台風の対応についての決定は、本日の午後以降になりそうです。
決まりしだい、HP,安全メールでご案内いたします。
台風10号接近について【8月29日】
台風10号接近による措置(登校時間変更、休校等)については、8月30日の12時までに、このHP、安心・安全メールでお知らせします。
2学期に向けて【8月29日】
8月28日(水)は、2学期に向けての職員会議、そして夏の研修についての研修報告、今後の授業研修の計画を立てました。
職員も2学期が始める準備をしています。始業式に、みんなが元気に登校してくることを心待ちにしています。




5・6年生登校日【8月27日】
今日は、夏休み中の最後の登校日であり、5、6年生の登校日でした。各学級で提出物の確認やアクティビティ、笛の練習。5,6年生の運動会の係の顔合わせを、ランチルームで行いました。その後、マーチング練習を合同で実施し、下校しました。家庭の予定や体調不良もあって、全員出席ではなかったです。
次は、いよいよ2学期の始業式。9月2日に会いましょう。










入善高校前地下道開通
入善高校前から入善小学校前につながる地下道が27日より、開通いたしました。これまで8号線横断をしていた子供たちは、これからは地下道を通ってください。同時に、小学校前の車道も開通したため、学校前の車の通行が多くなっています。送迎の方は、これまで通り、体育館側の駐車場での乗り降りをお願いいたします。引き続き、ブックマーケット側の地下道の工事が始まります。






宿泊学習下見へ【8月26日】
6学年の宿泊学習が、10月に予定されています。夏季休業中の方が、下見に時間をかけられるので、4人の教員で行ってきました。場所は、立山青少年自然の家です。今回、6年生には、コロナ渦でできなかった活動も提示し、子供たちが選んでくれれば、ぜひ体験してほしいと思っています。そのために、若手教員が多いので、コースの下見、アクティビティの体験をしてきました。詳細は、6年生と合意するまで書けませんが、面白い宿泊学習になることでしょう。




