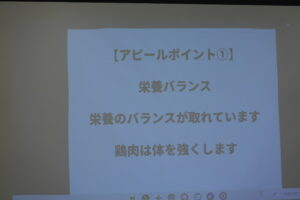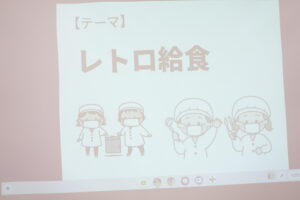1月23日(金)、大雪や通行止め等を心配しましたが、6年生のスキー学習を実施いたしました。学校から黒部ICまでが渋滞しましたが、その後は予定通りに到着しました。青空も覗いた天気、雪質もよく、怪我もなく、いい思い出になったようです。らいちょうバレーのインストラクターのレッスンですので、安全であり、必ず上達します。これで、人生最後のスキーになる子も多いと思います。大事な機会であり、まずは実施できたことがよかったです。
















カテゴリー: 6年生
スキー学習終了(6年)【1.23】
6年生スキー学習から帰校し、解散しました。大寒波の予想でしたが、天候は晴れと曇り。雪質もよく、「上達した」という子もたくさんいました。来週から、やり残しのないように小学校生活を送りましょう。


スキー学習(6年)【1.23】
6年生は、らいちょうバレースキー場に到着したそうです。天候は、曇り。
スキー学習(6年)【1.23】
6年生が、最後のスキー学習へ出発しました。降雪、道路状況が心配されましたが、実施することができました。北陸自動車道が、朝日~黒部間が閉鎖中ですので、黒部ICから立山へ向かいます。出発時は青空も見えました。今朝も体育館裏の駐車場がきれいに除雪されています。ありがとうございます。6年生、まずは怪我なく、楽しんで帰ってきてください。




6年生らしい実験【1.22】
6年生の理科。「水溶液の性質」の学習。炭酸水から二酸化炭素を取り出し、それが二酸化炭素であることを、「石灰水」で確かめてます。今日は、火のついた線香を入れて、「火が消える」ことで、「酸素」ではなく、「窒素」か「二酸化炭素」であることを確認しています。実験を見ていると、手際がよく、試験管に素早く栓をしています。いろんな技能が集約された実験です。これができるようになれば卒業です。




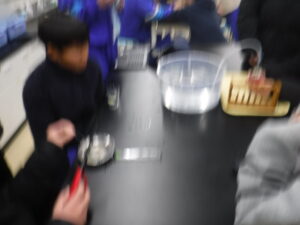

鉄棒しあげ(6年)【1.20】
6年生の体育。太田先生の授業ですが、山本先生も参観。「てつぼうルーム」と「なわとびルーム」に分かれて学習。なわとびルームは、2本のロープを使う「ダブルダッチ・ジャンプ」に取り組んでいます。鉄棒は、もうすぐ「最後のテスト」ということで、これまでの技の確認と練習でした。雪が降っていますが、温かいのがいいですね。恵まれた環境です。


標準学力調査(6年)【1.16】
6年生は、今日は「国語」と「算数」の標準学力調査の日です。もちろん、真剣に取り組んでいます。毎年、このテストが終わると、そろそろ卒業が近づいてきたと感じます。学習をしっかりと仕上げていきましょう。


長縄(6年)【1.16】
6年生の体育は、「鉄棒と長縄」です。「てつぼうルーム」と隣の「なわとびルーム」で交代しながら、取り組んでいます。6年生は、昨年の「ながなわ大会」では、卒業した6年生(2学級)に続いての全校3位でした。たしかに跳び慣れています。しかし、まだ縄の回し方はゆっくりですので、4年生が6年生を超えてくるかもしれません。全校的に「長縄8の字跳び」に取り組んでいます。




いっしょになわとび(1,6年)【12.23】
体育です。1年生と6年生が一緒に短なわとびをしました。6年生がペアで回数を数えてくれて、教えてくれます。今日、はじめて「後ろとび」ができた1年生もいました。6年生が優しいので、1年生は安心して取り組めます。1年生の一生懸命な姿を見て、6年生もまた、練習し始めます。異学年体育もいいものですね。








リクエスト給食②(6年)【12.19】
リクエスト給食のメニュー発表の2日目です。今日は、3組のグループが「メニュー」を発表してくれました。これで5つのメニューが揃いました。タブレットから全校児童・教員の投票から、2つのメニューが選ばれます。実際に、どのメニューが給食に並ぶのでしょうか。3学期の楽しみが増えましたね。