先日は、教員を対象に校内研修で「短距離走」の研修を受けました。講師は、岡本教頭先生です。教頭先生は、短距離走が専門で、現在も県の陸上の役員を務めておられます。今日から希望する学年で、教頭先生の「短距離走」の特別授業が始まりました。1回目は、3年生で実施しました。3年生は、とても素直なので、すぐに上達していきます。今日は、4限目に「5年生」での特別授業も実施します。




投稿者: 入善小学校
日本を地図から(5年)【4月22日】
5年生の社会科。A組、B組ともに豊嶋先生の授業です。日本とその周辺から、社会科が始まりました。日本が島国であること、たくさんの小さな島があること。そして、その小さな島が領土として大事であること等を学ぶのです。ぜひ地図を眺めるのが大好きな5年生になってほしいものです。




トレーニングも(3年)【4月22日】
3年B組をのぞくと、集中しています。何かなと思ったら、「100マス計算」でした。しかも、九九の100マス計算です。いいですね。九九は、2年生で学習しても、たまに使って行かないと「駆動」してくれないのです。特に、これからわり算の学習をしていく3年生には、トレーニング的に「きたえる」時間も大事なのです。本校のAIドリル「タブドリ」は、現在、新年度の契約の更新中で、もうしばらく使えません。もうしばらくお待ちください。


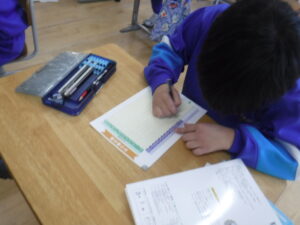

今日の1年生【4月22日】
さんすうの時間。できるようになりたい、がんばりたい。そんな気持ちが体によく表れているのです。「線のつなぎかた」についても、反応が多く、たくさんの手が挙がります。森田先生の話では、「考えを話すことに慣れている」「はずかしがらずに話せる」そうで、保育所でよく育ててこられたことがわかります。今日も一日で、ぐんぐん成長しました。




外国語活動(2年)【4月21日】
2年生になっても、ジェイク先生との「外国語活動」、盛り上がっています。「△ 〇 」等の形の「英語での言い方」です。ジェイク先生のネイティブな発音が、子供たちにすーっと入っていきます。うらやましい環境です。






今日の1年生【4月21日】
「先週より、話がとおりやすいのです」と森田みほ先生。土、日を挟んだのに、それはすごいことです。「手をぴんと挙げています」と先生が言うと、一段と手が伸びます。素直です。素直だと、とても伸びるのです。




静から動(3年)【4月21日】
3年A組の国語科。クラス替えをしましたが、「聴ける」教室です。「考えを話し合いましょう」の浜岡先生の言葉で、「静」から「動」へ。動くときも落ち着きがあり、相談する相手を見つけては、話し合うことができます。4月の時点で、もうここまでできていることに感心しました。






友達の絵を鑑賞(4年)【4月21日】
4年生B組。隣の教室の友達の絵も「鑑賞」しています。他の人の作品をじっくり見てみると、「見えてくる」ことがあるんですね。「こんな作品をつくるんだ」という驚きもあります。地味ですが、いい活動です。



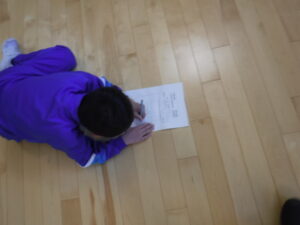
ものの燃え方(6年)【4月21日】
ろうそくと線香を「ふた」のある、ないで「燃え方」について考えていきます。とても面白いところです。ふたをしめても、ふたを開けても「火が消える」不思議。どのように検証実験を考えていくか楽しみですね。
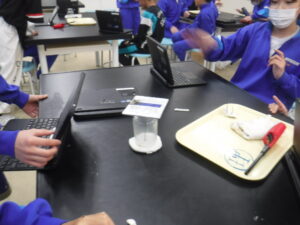



学習参観でした【4月18日】
1年生 生活科。「わくわく広場」を会場にしてよかったです。たくさんの保護者でいっぱいでした。さすが1年生の初めての学習参観です。




2年生 国語科。ふきのとう。




3年A組 算数


3年B組 国語


4年A組 社会科


4年B組 算数科


5年A組 国語科


5年B組 社会科


6年生 学級活動




